変わる金融機関
金融庁の発足から20年。
監督官庁が果たすべき役割とは何かと、自問自答する中で練り上げた新たな行政方針を基に、
金融庁の思惑を読み解く。
資産運用
資産運用では、投資信託を販売する金融機関の姿勢に注文が付いた。
行政方針では、その根拠となるデータが二つ示されている。
一つ目は、販売会社となる主要銀行や地銀、証券会社それぞれの顧客に関する投信の平均保有期間を示したものだ(図参照)。いずれも、15年度末を境に短期化しているのが分かる。
平均保有期間は、2年未満から4年超まで「販売会社ごとに大きな差がみられる」とされる。
保有期間が長いほど損失を出す顧客の比率が減る傾向にある中で、長期投資の重要性を説く金融庁の方針とは、逆行する動きになっているというわけだ。
二つ目は、メガバンクなど主要9行や地銀20行の営業店に対して実施した、月々の「リスク性商品」(投信と一時払い保険)の販売状況の検証結果だ。
四半期末ごとに販売額が拡大する傾向があり(図参照)、特に「運用環境に左右されにくい一時払い保険において顕著な増加がみられた」としている。
こうしたデータを踏まえ、金融庁は「営業現場では、収益目標を意識して、期末に向けてプッシュ型営業により、特定の顧客に対し乗換取引を繰り返している可能性が窺われる」と明記。
金融機関による「回転売買」に、あらためてクギを刺した格好だ。
かつて問題視された毎月分配型の投信に関しては、森前長官が批判の矛先を向けた途端、業界が一気に自粛ムードへ動き、販売額が急減した経緯がある。
そうして投信業界は浄化が進んだと、胸を張る関係者も少なくなかったが、今回の行政方針には、
依然として「顧客本位の取り組みは道半ば」という金融庁の怒りにも似た思いが随所にうかがえる。
貯蓄から投資へのスローガンで国を挙げて個人資産形成を促しても、いままでの投資=損をする
損をするぐらいなら 0.001%の金利の普通預金の預けて置いた方がまし・・・
しかし、この20年間で個人資産の伸びは「米国人は3.3倍」に「日本人は1.5倍」となり格差はどんどん広がっています。
食わず嫌いをやめて 資産形成に目を向けてみませんか。
すべての人にお金の教養を!
ファイナンシャルプランナー ロペオ
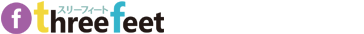
Leave a Reply