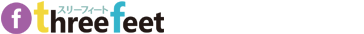誰が一番税金を納めているか・・・
実は一番税金を納めている「サラリーマン」
では、効果節税方法とは、
消費税増税の時期も近づいてきています。このような状況から、
「効率的な節税方法はないのだろうか?」
と思っているサラリーマンも多いのではないでしょうか。
サラリーマンでなくとも思うことかもしれませんが、
サラリーマンがこのように感じることが多いのは課税状況にあるといえます。
実はサラリーマンが一番税金を納めていると言われているのです。
クロヨン(9・6・4)とか、トーゴーサン(10・5・3)という言葉がありますが、
これは本来課税対象とされるべき所得のうち、
税務署がどの程度を把握できているかを示す言葉です。
この言葉はサラリーマンが9~10割捕捉されているのに対して、
自営業者は5~6割、農林水産業者は3~4割の捕捉となっていることを示します。
もちろん、これらの数字に確固たる根拠があるわけではありませんが、
サラリーマンが最も税金を納めていると言われています。
このこと自体は、税金を支払うという面で透明性があり、良いことではありますが、
不公平だと感じる人もいることでしょう。
そこで、一番税金を納めているサラリーマンが行なえる、最強節税方法を紹介したいと思います。
なぜサラリーマンは課税されやすいのか?
サラリーマンの場合、税金の知識が少ない人が多いため、
節税に目が向かないといったことも大きいのではないでしょうか。
それに対して自営業者などは「税金は日々の生活にも影響してくるもの」という認識があります。そのため、いかに売上げ、利益を構築し、節税を図るか、という視点も強くなります。
iDeCoとは、(確定拠出型年金)
自身が掛金を拠出し、その掛金をもとに運用を行なう私的年金です。
運用は自分で行なうことになりますので、運用結果次第では大きく増やし、
老後資金の構築を図ることができます。
一方、損失を被ることもあるため、中長期的にどのような運用を行なっていくことが望ましいのか、
しっかり検討する必要があります。
メリットは、拠出した掛金がすべて所得控除の対象となり、所得税や住民税を計算する際に所得から差し引くことができます。
つまり、支払った掛金分の所得が課税対象とならないのです。
仮に、所得税率が最高の45%だった場合、支払った掛金が年間で24万円だとすると、
24万円×45%=10.8万円の所得税節税を図ることができます
(状況によって変動の可能性あり)。
税率の高い人ほど節税メリットが大きくなっています。
積立時(所得税・住民税が軽くなる)
運用時(運用益も税金が0円に!一般的には金融商品は運用益に対して20%の税金がかかります。)
受取り時(受取り時も税金が軽減される)
(積立で一時で受取る場合、他の退職所得と合算して1500万円まで非課税)

年収500万円の人で月々2.3万円の掛け金の場合、
年末調整にて約4万円の還付となります。
年収1000万円の人で月々2.3万円の掛け金の場合、
年末調整にて約9万円の還付となります。
年収に関係なく普通預金に月々2.3万円の貯蓄をした場合、
年末に(1年間)で約1円の金利(還付)となります。
しかも、iDeCoでは、運用益が非課税になります。
また、受取り時には一括で受け取り、時受け取るか年金で受け取るかを選択しますが、
さらに、iDeCo一括の場合には退職所得控除として課税がかなり抑えられるようになっています。
年金として受け取る場合には公的年金等控除を利用できるため、
受け取る年金にそのまま課税されるのではなく、課税対象を抑えることができるようになっています。
このように、拠出時、運用時、受取時の
いずれにおいても税制面のメリットがあるのがiDeCoです。
老後資金構築方法として優れた役割を果たすことが可能です。
ぜひ、利用してみてはいかがでしょうか。
すべての人にお金の教養 ファイナンシャルプランナー ロペオ