セカンドライフの変化
社会保障費が上がり、年々、年金受給額が減ってきています。
年金だけでは不足してしまうため、生活費はそれまでに貯めていた
私の祖父母の時代は、平均寿命が72歳くらいでした。(昭和50年頃)当時は60歳定年も多かったため、セカンドライフは約10年強ということになります。金利も高かったため、
では、現在はどうでしょうか?「老後格差」や「下流老人」などの
セカンドライフは思っていたよりも現役時代と比べて支出が変わり
<毎月の収支のマイナス分
毎月の支出 23万円
ご夫婦の年金 20万円(マイナス3万円)と仮定
*退職から平均寿命までの20年で計算
月3万円×12ヶ月×20年=720万円
*退職から30年で計算すると…
月3万円×12ヶ月×30年=1080万円
平均寿命までの20年で計算しましたが、年々、平均寿命は延びて
また、社会保障費(保険料)も年々上がり、受け取れると思ってい
セカンドライフの生活費を考える際は、余裕を持って試算するよう
すべての人にお金の教養を!
ファイナンシャルプランナー ロペオ
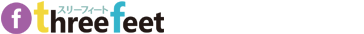
Leave a Reply