投資信託の基本
投資信託への資金流入の勢いが回復している、という話が出ています。QUICK資産運用研究所によると、8月の資金流入額は2697億円で、7月(1222億円)から大幅に増加したとのことです。
では、投資信託とは何でしょう。
株式投資の初心者が実際に株式を購入するに当たって、2つのハードルがあります。
株式銘柄と資金です。
まず、「どの株式銘柄を買ったら良いのか」が分からないことが最初のハードルです。だからといって、「自分の会社のことならば様子が分かるので、自社株を買おう」という考え方は危険です。会社が順調に成長し利益を稼げば問題ありませんが、会社が傾いたり倒産したりしたときに、勤務先と退職金と自社株を一気に失ってしまうリスクがあるからです。
すなわち、1つの株式銘柄に自分の運命を預けるのは、大成功する可能性もある半面、危険が伴います。
どんな場面に陥っても最悪の事態は避けたいと思う人もいるでしょう。
個人では分散投資がしにくい。
その観点からは、株式投資も、1つの銘柄を大量に保有するのではなく、数多くの銘柄に少しずつ投資して、何が起きても酷い目に遭わないように備えておくことができればいいわけです。
ここで2つ目のハードルが登場します。
東証上場銘柄は、100株単位でしか取引ができないのです。
手持ちの資金が10万円として、「10銘柄を1万円ずつ購入する」といった買い方はできません。
10銘柄の購入には、数百万円もの資金が必要となりかねず、普通の会社員には難しいでしょう。
そこで、考え出された商品が「投資信託」です。資産運用会社が多数の人から集めた小口の資金をまとめて株式や債券に投資し、収益が出た分から手数料を差し引いて出資者に返還する仕組みです。
これであれば、少額で投資できますし、
自分で銘柄を選ぶ必要もありません。
多数の銘柄に投資しますから、リスクの分散にもつながります。
投資信託には、投資対象が「日本企業の株式」だったり「米国企業の株式」だったり「世界の債券」だったり、さまざまな種類があります。さらには、「日本株式と米国株式と債券」を組み合わせた「バランスファンド」という商品もあります。
初心者であっても、自分が気に入った投資信託を選べばいいのです。
運用方針による投資信託の違い
運用方針による違いもあります。ファンドマネジャーと呼ばれる投資のプロが購入する銘柄を選定するタイプが「アクティブファンド」です。値上がりする確率は高そうですが、支払い手数料も高くなります。
「日経平均株価の計算に使われている225銘柄の株式をすべて1000株ずつ買う」といったタイプは「パッシブファンド」=「インデックスファンド」です。手数料が安い点が取り柄です。
手数料については、購入時に1回だけかかる「購入時手数料」と、
保有期間中にかかる「信託報酬(運用管理費用)」があります。前者は入会金、後者は年会費のイメージですね。この手数料、実はバラバラで、高いものと安いものが混在しています。
特に注意が必要なのは、年会費に相当する信託報酬です。老後資金を若い時から投資信託で数十年間運用する場合など、信託報酬が年間1%異なるだけで手にできる金額に極めて大きな差が出てきます。
金融機関は、一般的に手数料率の高い投資信託を販売したがる傾向があります。
また、購入時手数料を目当てに、新しい投資信託への乗り換えを勧めがちです。
預金が安全とは限らない
長期間の運用を考えるのであれば、「積立NISA」でコツコツと投資信託を買い増すという選択肢もあります。
税制上のメリットが大きいうえに、手数料が安い投資信託だけを金融庁が選んで積立NISA対象商品としているからです。
手持ちの現金のうち、どれぐらいを銀行に預け、どのぐらいを株式に投資すればいいのか――。
それは「どれくらいリスクを覚悟して利益を狙うか」という個人の判断にかかっています。
「預金しておけば安心」と考える人もいるでしょうが、預金はインフレが来ると目減りしかねない“リスク”を抱えていることは頭に入れておきましょう。
すべての人にお金の教養を!
ファイナンシャルプランナー ロペオ
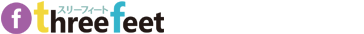
Leave a Reply