今度こそ受け皿になれるか
「貯蓄から投資へ」の受け皿として期待される投資信託だが実態はあまり進んでいない。
日銀によれば2018年3月末時点の家計金融資産は約1829兆円。このうち投資信託の割合はわずかに4%。株式10.9%を下回り、現預金52.5%の10分の1以下だ。
証券業界ではかねて、商品を「売る側」である販売会社の発言力が強い。
販売会社は「作る側」の運用会社に対し、売りやすい商品や手数料を稼ぎやすい商品を要求する。
こうした、いびつな力関係が、新規設定の乱発や別の投資信託に乗り換えさせることで手数料を稼ぐ「回転売買」の温床になってきた。
販売会社主導で大きく成長した投資信託の
代表格が「グローバル・ソブリン・オープン」
通称「グロソブ」だ。ピークの2008年には残高が5兆8000万円達し、
住民の多くが「グロソブ」を保有する香川県小豆島は「グロソブの島」と呼ばれ話題を集めた。
「グロソブ」は毎月分配型が主流だが、金融庁は毎月分配型を長期の資産形成に不向きと批判。「グロソブ」の純資産は現在、約4300億円と1割以下まで減っている。
一方、米国では家計金融資産に占める投資信託の割合は11.8%と日本の約3倍に達する
日本でも大手銀行が投資信託の販売手法を見直し、業績の評価基準を新規販売額から残高に切り替えるなどストック型(契約残高)へのビジネスモデルの転換の動きが出てきた。
しかし金融庁は2018年事務年度の金融行政方針で、投資信託について「四半期ごとに販売が増加している」と指摘。
そのうえで、投資信託の平均保有期間や顧客数が伸び悩んでいることを踏まえて「収益目標を意識して、特定の顧客に対して乗り換え取引を繰り返している可能性が疑われる」とした。投信業界に向けられる視線は依然として厳しい。
人生100年時代の到来を迎え、投資家にとって安定した資産形成が重みを増してきた。
今度こそ「貯蓄から投資へ」の受け皿になれるか、投信業界の覚悟が問われる。
すべての人にお金の教養を!
ファイナンシャルプランナー ロペオ
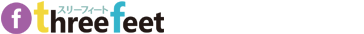
Leave a Reply