定年までに3000万円貯りますか?3
銀行と保険会社を守らざるをえない日本のお国事情
「情報の崖」があるので、良い金融商品がどこにあるのか私たち日本人には分かりません。
「まともな金融商品」は海外にたくさんありますが、日本の金融商品取引法、保険業法等では、それらを紹介することを禁止しています。
資産分散の選択肢が狭められていることさえ、誰も知らないのです。
「金融が自由化されているはずなのに、なぜ?」
と気付いた方は、鋭い方です。
確かに、橋本内閣時代に金融自由化がはじまりました。
しかし、自由化とは名ばかりで、
「銀行が日本の投資信託や日本の保険を売っても構いませんよ」
という内輪だけの自由化でした。
なぜ、中途半端な自由化しかできなかったかというと、
「お金の知識がない私たちを守るため」だそうです。
確かに表向きはそうなのですが、それだけならお金の教育で事足ります
本当のところは銀行や保険会社を守らざるをえない裏事情があったのです。
もし、海外の金融商品に皆が気付くと、日本の銀行や保険会社は見向きもされずに潰れます。
そうならないように、「情報の崖」を作って私たちに目隠しをしていたのです。
世界一の借金大国日本が財政破綻しないのは・・・
国債の大半を外国人ではなく日本人が持っているからだと言われています。実際には、個人から預かった、預貯金や保険料を元手にして、銀行や保険会社が大量の国債を持っている、という構造になっています。
つまり、日本の安泰は「国民からお金を吸い上げる銀行や生命保険会社あってこそ」なので、金融機関を守るのは当然です。
その代わりとして国が「情報の崖」で金融機関を守り、金融機関は国債を買って恩を返す、という暗黙の了解があったのです。
年金の寿命を縮めた延命治療・・・
年金さえまともにもらえるのであれば、金利が低くても、投資信託の手数料が高くても、海外の情報を知らなくても、一向に構いません。
そう考えると、もらえる年金額が確実に減る「年金の崖」が諸悪の根源ということになります。
国から支払われる年金の仕組みは2種類あります。
①自分のお金を自分で積み立てて、それを未来の自分が受け取る方式(積立方式)と、
②働いて納めたお金を、見ず知らずの高齢者が受け取る方式(仕送り方式)です。
日本は長らくずっと、「収入のない高齢者に対して、働いている誰かがお金を渡す」②仕送り方式でした。
実は、日本の仕送り方式には、致命的な欠点が2つあります。
その2つの欠点ゆえに、将来もらえる年金が半分に減ります
1つ目の欠点は、将来人口が減ることを織り込まなかったこと
2つ目の欠点は、納められた年金資産を長期間運用することができないということ。
日本人は戦前と比べて30歳も長生きするようになりました。
それ自体は喜ばしいことですが、年金がこれについてこられませんでした。日本の財政悪化の一番の原因は医療費等の社会保障費の増加です。
働く世代が払う年金掛金が減り続ける一方で、年金という制度自体が
死なないように延命させる治療法は2つしかありません・・・
①お年寄りに泣いてもらう
年金支給開始時期を10年ほど後ろにズラして75歳にするか、年金支給額を半分に減らす
②若者にしわ寄せする
働く世代の納付額を2倍に増やすか、納付期限を10年伸ばして70歳まで引き上げる。
そこで、仕送り方式を補うために追加されたのが積立方式(確定拠出年金)iDeCoなのです
金融庁トップの森信親長官は雑誌「エコノミスト」のインタビューに答えて「公的年金など公的扶助の仕組みにはおのずと財政的な制約がある」と述べ、「貯蓄を賢く分散投資して資産形成しなければならない」と発言しているわけです。
確定拠出型年金(iDeCo)積立てNISAなどは、元本割れるするのでは?私には関係ない!
では、すまされない。国任せから自己責任へ!
年金問題というと、将来もらえる年金額が減ることばかりに目が行きがちですが、日本の年金はもっと厄介な副産物を生み出しました。
それは、行きすぎた社会保障と所得税の源泉徴収制度が、
「私たちを過保護にしたせいで、お金を管理する能力が退化」した、ということ。戦後の高度成長期の日本では社会保障がしっかりしていたから、お金の勉強をせずに「国任せ」にしても心配ありませんでした。
会社も従業員を家族のように大事にしたので、路頭に迷うことはありませんでした。
その結果、お金について勉強する必要はなく、むしろ「お金儲けは後ろめたい」という風潮が生まれてしまいました。お金の管理の「自己責任」を自ら放棄してしまったのです。
結果的に税金や社会保険料のムダ遣いに対しても無関心になりました。
こうして日本人に染み付いた感覚は、将来への不安はあるものの、お金を儲けることへの罪悪感があって、資産を運用してお金を増やすこと(不労所得)に抵抗を感じるようになったのです。
実は、このような現象は、日本だけに限ったことではありませんでした。ヨーロッパでは1980年頃に経済成長が鈍くなって、個人の所得が伸びなくなりました。
いまの日本と同じ状況です。その後、個人資産が貯金から投資へと流れたことがきっかけで、再び個人の所得が伸びるようになりました。
たとえば産業の空洞化に悩んだイギリスは、金融の国として成長することを目指して政策の大転換を行い、 1986年に金融ビッグバンを起こしました。これをきっかけに、証券会社・銀行・保険会社など、あらゆる金融サービスの規制が緩和されました。裏を返すと、「お金のことは自分で何とかしろ」という方針になったのです。
そして、ここが大切なポイントなのですが、お金のことを自分で何とかできるようにお金の教育が強化され、学校ではお金の授業が必須科目となったのです。
もともとはイギリス人も「働かずに儲けるなんてふざけている」と考えていました。
そこで、「投資は悪いことではなく、老後の生活費のために必要なこと」だという考え方を、学校教育のなかに取り入れたのです。
他人任せ、官僚任せ、政治家任せ、国任せにしすぎたのかもしれません。いままで放棄してきた「自己責任」というスコップを取り戻して落とし穴を埋めないと、私たちがそこに埋められて、貧乏なままで人生が終わってしまいます。
自分なりにまとめてみました。さらに詳しく読みたは是非ご一読してみてください。
すべての人にお金の教養を ファイナンシャルプランナー ロペオ
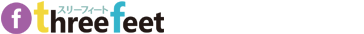
Leave a Reply