知らないばかりに不要な税金を払っていなですか?2
100万円超のリフォームは控除対象か?
家は買っていないが100万円超のリフォームは控除対象か?
【解答】控除される。(*ただし、一定要件を満たすこと)
住宅ローン控除は自宅のリフォーム代も対象です。一定の要件さえ満たせば必要経費として認められます。
築20年中古の家(マンション)9年間のローンで中古の家を買った!
【解答】控除されない
残念ながら、返済期間が10年以上の住宅ローンでないと控除として認められません。この場合は対象外です。
「住宅ローン控除」(税額控除)税金控除の王様!
最大10年間、所得税が0円になることも!
サラリーマンにとってマイホームの購入は人生最大の買い物です。
その際は、ローンを組むことがほとんどですが、ここでも控除を受けられます。
基本的な条件は以下のとおりですが、節税効果は抜群に高いです。
住宅のリフォームでも一定の要件を満たせば対象になるので、うまく活用して家計の節約に役立てましょう。
住宅ローン控除を受けられる条件
・購入した住宅や増改築後の住居の床面積(登記簿上)50m^2 以上
・床面積の2分の1以上を住宅用としている
・中古物件の場合、配偶者や親族からの取得ではない(事実の婚姻関係も含む)
・新築・増築・改築から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいる
・借入金の返済期間は10年以上
・社内融資の場合、利子が1%以上(役員は除く)
・合計所得金額が3,000万円(給与収入のみで3,336万円)以下等の条件があります。
自宅購入初年度年末におけるローン残高が3,000万円なら、その1%=30万円が控除対象です。
年収500万円の人で年末残高3000万円の残高で、
還付金約20万円となります。(住民税含む)
「住宅特定改修特別控除」
自宅のバリアフリー改修工事や、省エネ改修工事を行った場合に適用される控除です。
階段に手すりをつけたり、寒さ対策で窓を二重にするといったケースを指します。
この控除は、次のような面倒なこともありますが、金額が大きいので、工事を予定されている方は活用したほうが良いでしょう。
・借入金の返済期間が5年以上
・改修にあらかじめ決められた材料を使わなければならない
・住宅の増改築の場合、工事費用が100万円超
「社会保険料控除」
フリーターをしている息子の社会保険料は控除対象か?
【解答】控除される。
扶養に入れている家族などにかかわる社会保険料は、親が全額支払うことで控除対象とみなされます。
「小規模企業共済掛金等控除」
投資信託を毎月、購入しているが、その掛け金は控除対象か?
【解答】控除される。
*(ただし、ある条件の下であらかじめ承認が必要となります。)
確定拠出型年金(401k・iDeCo)等の制度を活用すれば全額控除(上限あり)されます。
上記制度のもと、61歳から毎月1万円を掛け金を掛けているが控除対象か?
【解答】控除さない。
残念ながら、原則60歳未満の方が加入対象者となります。
確定拠出型年金(iDeCo等)で積み立てた掛け金は「全額所得控除」積立全期間適用
iDeCoで得する3つのポイント
積立時
所得税・住民税が軽くなる(掛け金が全額その年の課税所得から控除される)
運用時
運用益も税金が0円に(一般的には金融商品は運用益に対して20%の税金がかかります。)
受取り時
受取り時も税金が軽減される(積立で一時で受取る場合、他の退職所得と合算して1500万円まで非課税)
年収500万円の人で月々2.3万円(年27.6万円)貯蓄の人の場合
還付金約40,000円となります。(住民税含む)
【確定拠出年金を支払わない場合の納税額】
)年収500万円の納税額
所得税=237万円×(10%-9万7,500円)=13万9,500円
住民税=237万円×10%=23万7,000円
所得税+住民税=37万6,500円
離婚したら要チェック?! 母子家庭になると控除される?
【解答】控除される。
「寡婦控除」
寡婦控除の条件とは?
寡婦控除の条件12月31日時点で夫と
条件その1
・離婚した後、婚姻してない人 ・死別した後、婚姻してない人 ・夫の生死が明らかでない人
条件その2
・合計所得が500万円以下・死別した後・婚姻してない人・夫の生死が明らかでない人の方
条件その2・1(特定の扶養控除)
・扶養親族か生計を一にしている子がいる(所得要件はありません)
(離婚した後、婚姻してない人・死別した後、婚姻してない人・夫の生死が明らかでない人)
税金は、確定申告の時期を過ぎても更正の請求といって、申告し忘れた「寡婦控除」の手続きができます
手取りが多いのはどっち!?
退職金を「年金形式」でもらえる VS「一括」でもらう!
【解答】 一括
退職金や年金の手取りには、非課税枠であるそれぞれの「控除」をうまく活用するのがポイントです。
キーワードは「退職金控除」と「公的年金控除」
「退職金控除」
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は、80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
「公的年金控除」
108万円 公的年金控除70万円(65歳未満)
120万円 公的年金控除(年齢65以上)
「年金」が増えるほど、社会保険料が多くなるから注意!
「所得」に対して国民健康保険料と介護保険料がかかるようにまってきます。
と言うことをになり思いがけず税金や保険料の負担が重く「手取りが思ったより少かった」事態になりかねないので貯めたお金は「年金受取り」をするのではなく「一括」で退職金控除を上手く活用しましょう。
いくら税金を払っているのか?
いくら社会保険料をはらっているのか?知ることは
日本人典型的な他力本願!国や会社や親に任せすぎだと感じます。もう少しコスト意識(いくら引かれているか?)をしっかりもってもらいたい上でしっかりと控除(節税・還付)に目を向けてもらえばと思います。
すべての人にお金の教養を
ファイナンシャルプランナー ロペオ
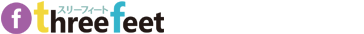
Leave a Reply